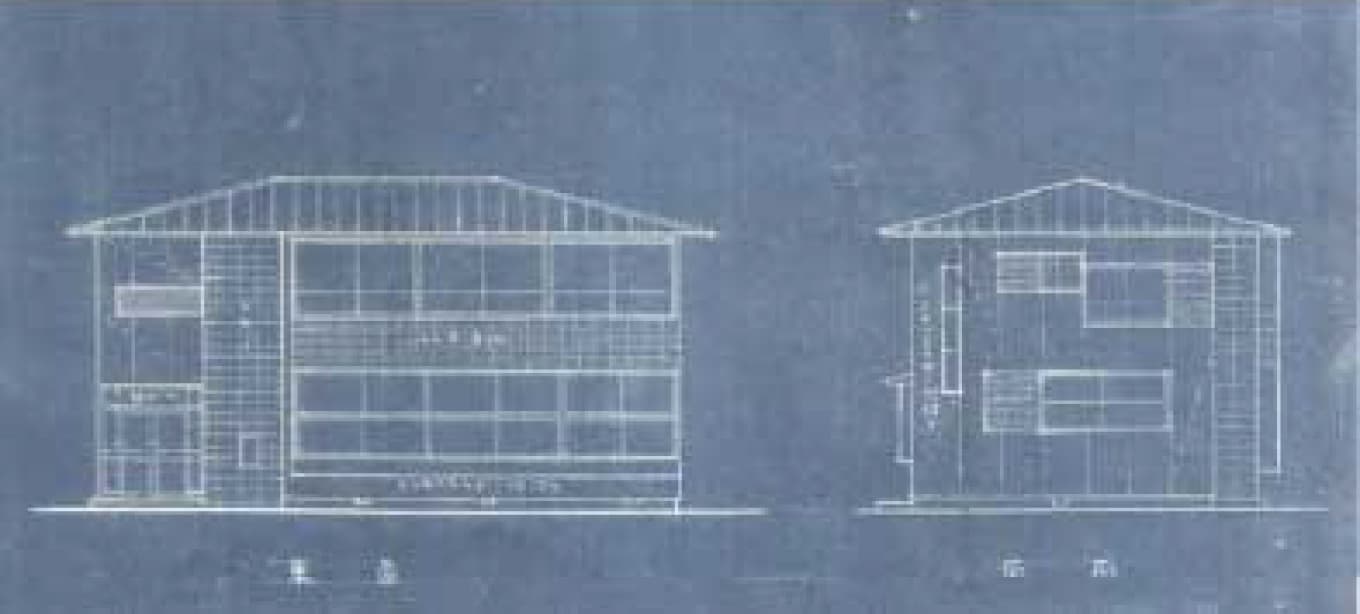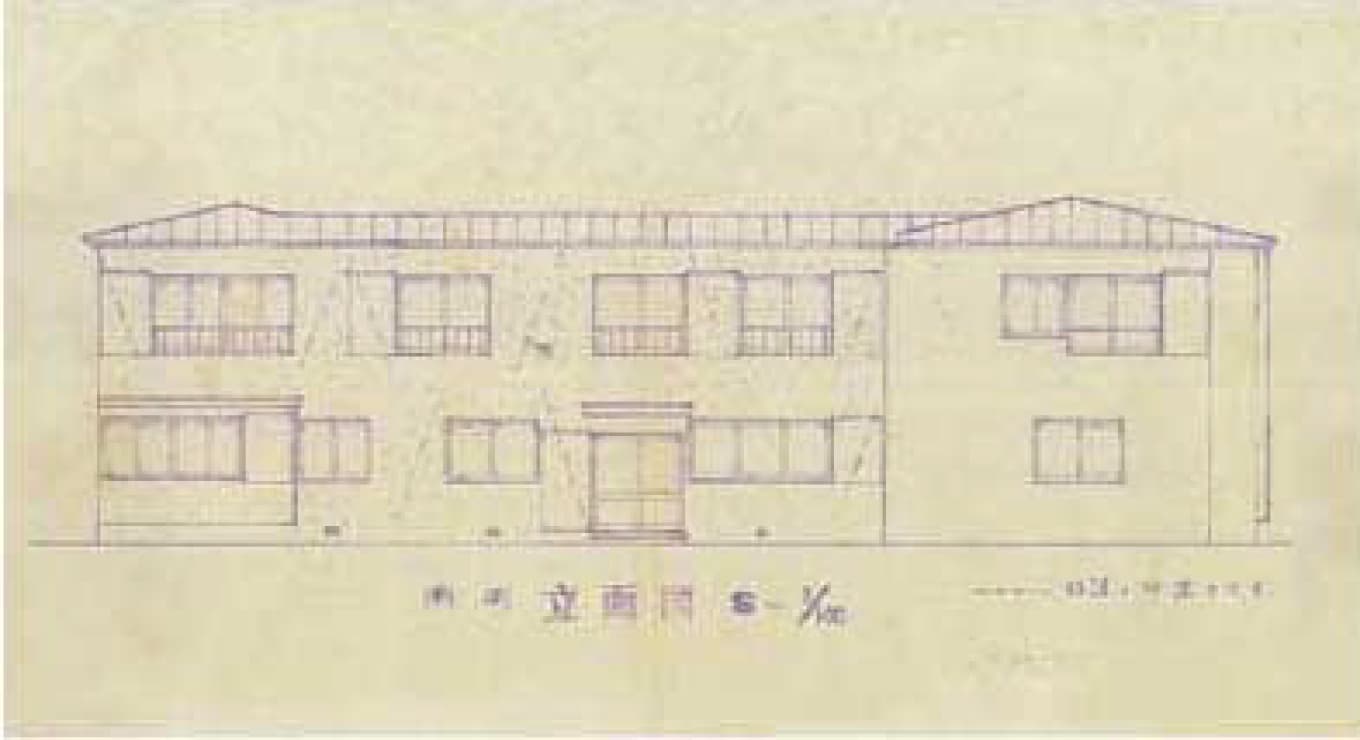当院について
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前受付 8:30 - 11:30 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 〜11:00 |
− |
| 午後受付 14:30 - 17:30 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
●診療時間:午前9:00~12:30 午後15:00~18:30
※土曜受付時間は11:00までになります。
※土曜日は原則予約診療となりましたので、予約システムより予約をお願いします。
※火曜午後、院長診察受付時間は17:00までになります。
※メガネ、コンタクトレンズの受付は受付終了1時間前までにお願いします。
※散瞳検査は受付終了30分前までにお願いします。